ピロリ菌を放っておくと?除菌の方法とその成功率について ピロリ菌シリーズ③
これまでのブログでは、ピロリ菌の感染経路、そして感染後に胃の中で起こる変化についてお話ししてきました。
最終回の今回は、ピロリ菌によって生じるリスクと、除菌の方法・成功率についてご紹介します。
ピロリ菌が引き起こす病気
ピロリ菌は、胃の中で長く炎症を起こすことで、次のような病気と関連していることが分かっています:
慢性胃炎 胃潰瘍・十二指腸潰瘍 胃がん 胃MALTリンパ腫(まれな悪性腫瘍) 特発性血小板減少性紫斑病(ITP)
中でもやはり注目すべきは、胃がんのリスクを高めることです。
実際、日本の胃がんの多くは、ピロリ菌の持続感染と関係していると考えられています。
除菌治療って、どうやるの?
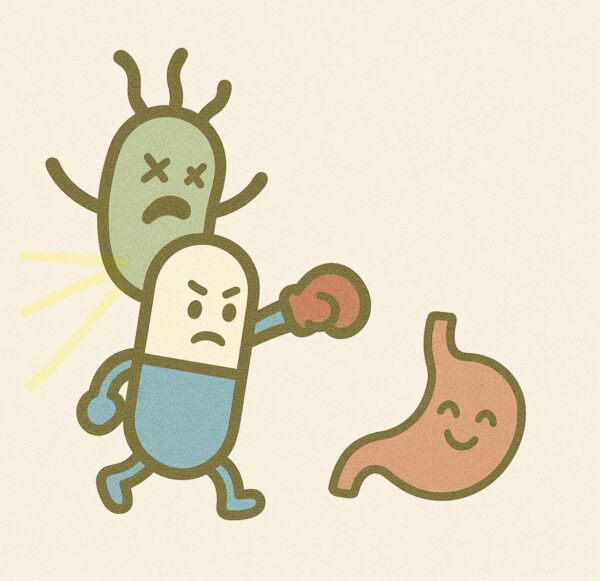
除菌治療は、抗生物質と胃酸を抑える薬を1週間内服するだけの比較的簡単な方法です。
具体的には、次の3剤を1日2回・7日間服用します:
抗菌薬(2種類) 胃酸抑制薬(PPIやP-CABなど)
治療後、約1ヶ月以上経ってから「除菌できたかどうか」を再検査します(呼気検査など)。
除菌の成功率は?
1回目(一次除菌)での成功率は**約70〜90%と言われています。
もし1回目でうまくいかなかった場合は、薬を変えて二次除菌(再挑戦)**が可能です。
二次除菌を含めると、9割以上の方が除菌に成功しています。
除菌は保険でできますか?
はい、保険で除菌治療を受けるには、まず胃カメラ(内視鏡検査)で“慢性胃炎”が確認されていることが必要です。
そのため、「ピロリ菌が気になる」「除菌を考えている」という方は、
まずは内視鏡検査を受けておくことが大切です。
当院では、できる限り苦痛の少ない内視鏡検査を心がけていますので、ご安心ください。
最後に
ピロリ菌は、一度感染すると自然には消えません。
でも、今では簡単な検査と薬の服用で、きちんと除菌できる時代です。
「まだ症状はないから」と様子を見ているうちに、胃がダメージを受けてしまう前に──
早めの検査と治療で、将来の病気を防いでいきましょう。
気になることがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。
